ぶりの漬け焼き

我が家では、日常ごはんからお正月のおせちにまで登場する一品。写真ではぶりを使っていますが、他の魚でもこの手法でおいしく食べることができます。
ただし皮目が上面を覆う魚(さば、あじなど)は焦げやすいので気をつけます。
材料(3~4人分)
- ぶりの切り身・・・3~4切れ
- ぶり用塩・・・ぶりの重量の1~2%
- 【A】酒、みりん、しょうゆ・・・各大さじ2~4(ポイント参照)
- しょうが・・・ひとかけ
<薬味>
- ゆずの皮、乾燥唐辛子・・・各適量
作り方
<ぶりの下処理をする>
1.ぶりの両面に塩をふって30分ほどおく。
※切り身が大きければ2分割にしても。骨がある場合は抜くのがおすすめ。

2.ぶりの表面に出た水分をキッチンペーパーでおさえる。
<ぶりを漬けて焼く>
1.密封袋に下処理が済んだぶり、【A】、おろしたしょうがを入れ、冷蔵庫で1時間~好みの時間漬け込む。

※漬け込み時間が長いほど味が深く入ります。
※おせちに使う場合は、大晦日の夜につけ込み元日に焼くというパターンがおすすめ。
2.1をグリルの網にのせ、両面こんがりと焼く。漬け込む時間が短い場合は、残った漬け液を途中何回か刷毛で塗るとよい。
※皮目の面積が広い場合など、焦げ目が気になり始めたら、上にアルミ箔を被せて続きを焼きます。

3.皿に盛り、あればゆずの皮、細かくした唐辛子をのせる。

上記はおせち用の盛り付けです。下に葉蘭を敷き、その上に漬け焼きをのせています。

おせち用にこんな盛り付け方も。漬け焼き自体が地味なので、おめでたい席では緑や他の色を添えると華やかになります。

日常ごはんではこんな感じになります。ゆずや唐辛子はなしの焼きっぱなし。これでも充分おいしいです。
ポイント
![]() 調味料の量はぶり全体がひたひたに浸かる程度を目安にします。酒:みりん:しょうゆ=1:1:1であればアバウトでかまいません。
調味料の量はぶり全体がひたひたに浸かる程度を目安にします。酒:みりん:しょうゆ=1:1:1であればアバウトでかまいません。
※しょうゆの味をしっかりめに利かせたい場合は、みりんを半量にしても。
![]() ぶりは腹側を選ぶと脂のりのいいおいしい漬け焼きになります(もちろん背側でもOKです。さっぱりと食べられます)。
ぶりは腹側を選ぶと脂のりのいいおいしい漬け焼きになります(もちろん背側でもOKです。さっぱりと食べられます)。
![]() 他におすすめの第一選択の魚は、皮目が少なめの切り身(例、まぐろ、めかじき、鮭、鯛、たらなど)です。皮目が多い魚(例:さば、あじなど)は焼くときに焦げ付きやすいので、上にアルミ箔を被せる、後半上火を弱火にするなどして気をつけます。
他におすすめの第一選択の魚は、皮目が少なめの切り身(例、まぐろ、めかじき、鮭、鯛、たらなど)です。皮目が多い魚(例:さば、あじなど)は焼くときに焦げ付きやすいので、上にアルミ箔を被せる、後半上火を弱火にするなどして気をつけます。
調理器具
![]() おせちの盛り付けに使っている角盛り皿はこちら
おせちの盛り付けに使っている角盛り皿はこちら
他の魚例
鯛バージョン

あじバージョン

まぐろバージョン

これはグリルではなくフライパンで焼き、漬け込んだタレを後半で加えて仕上げています。
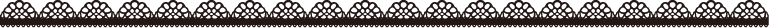
おすすめの追加メニュー(献立)
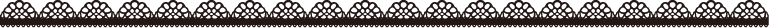
このレシピについて
![]() ブログ「Quality of Life by JUNA」には初期から登場
ブログ「Quality of Life by JUNA」には初期から登場
![]() 2015年著書『ほめられおせち』P38~39に掲載
2015年著書『ほめられおせち』P38~39に掲載
![]() 2023年12月第32回オンラインレッスンに登場
2023年12月第32回オンラインレッスンに登場
レッスンダイジェスト版はこちら↓
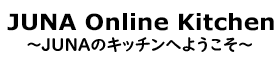
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3b6a3266.d71453a4.3b6a3267.935fdd29/?me_id=1262942&item_id=10109351&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Finterior-palette%2Fcabinet%2Fmaker_miyamoto4%2F342058.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


