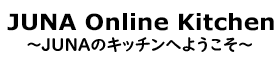いりこの特徴と選び方

いりこの種類と特徴
いりこ=煮干しのことで、魚の煮干しを使っただしの総称を「いりこだし」といいます。カタクチイワシの煮干しがよく知られていますが、真いわしやうるめいわしで作った煮干し、あご(トビウオ)の煮干し、鯛の煮干しなどもあります。
いずれにしてもいりこは魚を丸ごと使っているので、かつお節と比べると魚の味が出やすいのが特徴。魚のうま味を上手に引き出すためには、質の良いいりこを選ぶことがとても大切です。
いりこのうま味成分は「イノシン酸」。「グルタミン酸」との掛け合わせてそのうま味は増幅します。グルタミン酸といえば昆布。いりこ×昆布でもおいしいだしをひくことができます。
※ここでは主に、「カタクチイワシ」の煮干しについて述べます。
| ー目次ー カタクチイワシの煮干し 質のいいカタクチイワシの煮干しの選び方 1.美しい白銀の色をしていること 2.「へ」の字の形をしていること 3.軽い煮干しを選びましょう 4.大きさは味の好みによります カタクチイワシとあご(トビウオ)の煮干しの比較 いりこの保存方法 各いりこだしのひき方 いりこだしを使った料理例 執筆者 |
カタクチイワシの煮干し

いりこだしの素材として代表的な「カタクチイワシ」の煮干しですが、太平洋や日本海で獲れる背が黒っぽい「青口」、瀬戸内海などの内海で獲れる、全体的に白色の「白口」の2種に分かれます。稚魚の時は同じ色ですが、育つ環境によって色合いがかわり、だしの味にも違いが出ます。
写真は「白口」のカタクチイワシの煮干しです。
白口はまろやかなだしになり、青口はすっきりとしただしに仕上がります。

私は「白口」のカタクチイワシでひいたいりこだしが好みです!
質のいいカタクチイワシの煮干しの選び方
いりこだし全般に言えることですが、選ぶ煮干しの味がダイレクトにだしに出ます。質の悪い煮干しでだしをひくと、妙に魚臭くなったり生臭みが出たりするので、いい煮干しの状態を知っておくことが大切です。
質のいいカタクチイワシの特徴は以下の通りです。
1.美しい白銀の色をしていること

上記写真左のように、お腹部分が白っぽく、全体的に銀色が美しいものを選びましょう。写真右のように全体が黄色っぽい、お腹部分が黄味がかっているものは魚の脂肪分が酸化しています。酸化している煮干しでひいただしは生臭みが出がちです。
2.「へ」の字の形をしていること

新鮮な状態で加工されて煮干しになったものは、写真のように「へ」の字の形をしています。パッケージの外側から、「へ」の字の煮干しが多く入っている物を選ぶといいでしょう。
3.軽い煮干しを選びましょう
パッケージされているとなかなかわかりづらいかもしれませんが、いい煮干しはしっかりと乾燥されているので手に取ると「軽い」と感じます。もし、少し水分が残っていると感じた場合は、電子レンジやオーブンで軽く加熱して水分を飛ばすといでしょう。
4.大きさは味の好みによります
大きければいい煮干し、小さければ悪い煮干しということではなく、どちらも上記1~3の条件を満たしていればいい煮干しといえます。ただし、大きい煮干しは脂のりがいいことが多いのでコクのあるだしがひけ、小さい煮干しは脂肪が少ないのであっさりめのだしがひける、という味の違いが生じます。好みで選ぶといいでしょう。
カタクチイワシとあご(トビウオ)の煮干しの比較

参考までに、上が「あご」の煮干し、下が「カタクチイワシ」の煮干しです。大きさがかなり違います!
いりこの保存方法
開封後はしっかりと封をして冷蔵保存しましょう。煮干しは内臓や頭を含むため、開封と当時に酸化がはじまります。消費期限に限らず、冷蔵庫で管理しながらなるべく早く使いきるのがおすすめです。開封後は、2週間から長くても1ヶ月くらいの間で使い切ると、おいしいまま楽しめると思います。
それでもしばらく使わない場合は、密封袋に入れてできるだけ空気を抜き、冷凍してしまってもかまいません。真空パックにできる機械などがあれば、1度に使う文ごと小分けにしてパッキングするといいです。
各いりこだしのひき方



執筆者
![]() 家庭料理研究家:JUNA(神田智美)
家庭料理研究家:JUNA(神田智美)